問-6 正解 答えは × でした。
標準せん断力係数は地震の規模によって定まる係数でその値は中地震を想定した場合、0.2以上。大地震を想定した場合、1.0以上。その他木造の場合著しく軟弱な地盤で0.3以上と定められている。建築基準法施行令第88条第2項。
構造02 荷重・外力 問-10
下図のような方向に風を受ける建築物のA点における風圧力の値は、960N/m2である。ただし、速度圧は800N/m2で、→は風圧力の方向を示すものとし、1N=0.102kgfとする。
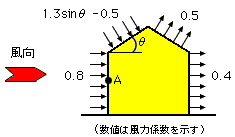
問-10 正解 答えは × でした。
風圧力は次式で求められる。
風圧力=速度圧×風力係数=800N/m2×0.8=640N/m2
問-12 残念 答えは × でした。
建築基準法施行令88条第2項により、地盤が著しく軟弱な区域として指定された区域内における木造の建築物の標準せん断力係数は、原則として、0.3とする。
問-13 正解 答えは ○ でした。
振動特性係数Rtは、一般に、建築物の設計用一次固有周期が長いほど小さい。告示(昭55)第1793号第2
問-17 残念 答えは × でした。
事務室の積載荷重は床の構造計算をする場合2900N/m2、大ばり、柱又は基礎の構造計算する場合1800N/m2、地震力を計算する場合800N/m2というように建築基準法令第85条に定められ、同じ積載荷重によって計算するのではない。
構造02 荷重・外力 問-20
多雪区域外における一般的な2階建の建築物の1階の構造耐力上主要な部分に生じる地震力は、0.2×(WR+W2) で求まる。ただし、地震層せん断力係数Ciは0.2とし、また、屋根部分の固定荷重と積載荷重の和をWRとし、2階部分の固定荷重と積載荷重の和をW2とする。
問-20 正解 答えは ○ でした。
建築物の地上部分の地震力は、その地震力を求めようとする階が支える上部の固定荷重と積載荷重の和(建物の重量)に、その階の地震層せん断力係数を乗じて求められる。したがって設問の場合は、地震力=0.2×(WR+W2)。建築基準法施行令第88条
問-21 正解 答えは × でした。
風力係数は、建築物の形状によって定められる係数で地盤面からの高さには関係ない。建築基準法施行令第87条第4項
問-22 正解 答えは × でした。
「床の構造計算をする場合の積載荷重」より「地震力を計算する場合の積載荷重」のほうが小さい。建築基準法施行令第85条1項
問-24 残念 答えは × でした。
建築基準法施行令第88条第4項により、地下部分の地震力は、地下部分の固定荷重と積載荷重の和に、水平震度kを乗じたものである。
水平震度kは次式で求める。
k≧0.1(1-H/40)Z
H:地下部分の地盤面からの深さ(20mを超えるときは20mとする)
Z:地震地域係数
これによって、建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、深さ20mまでは深くなるほど小さくなる。
問-25 残念 答えは × でした。
多雪区域において地震時における応力は固定荷重、積載荷重、地震力によって生じる力、積雪荷重(低減された)で地震時には風圧力は外力に含まず、G+P+0.35S+K となる。建築基準法施行令8条
No comments:
Post a Comment